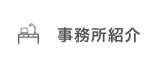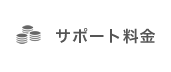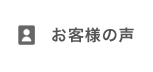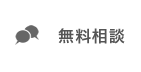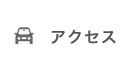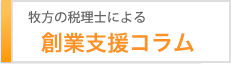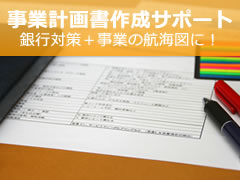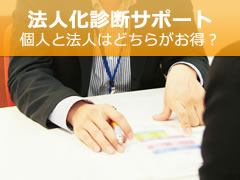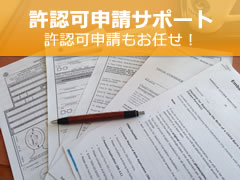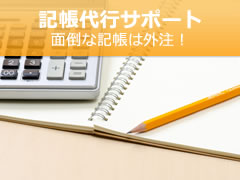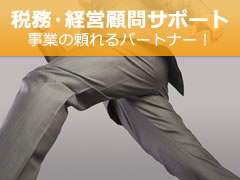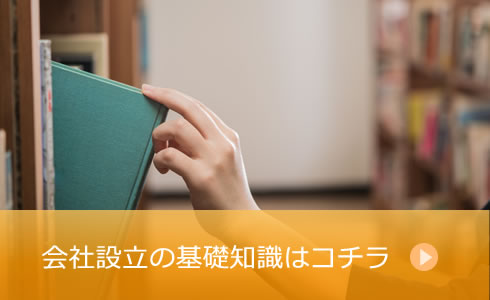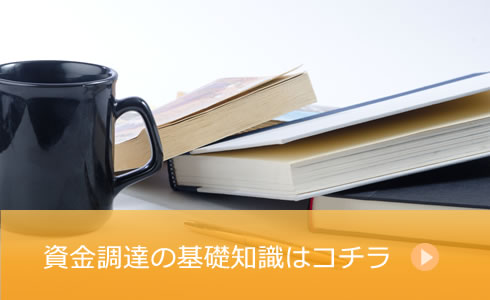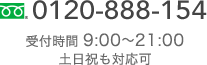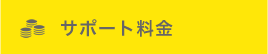新着情報
新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。
2020年も何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年度も非常に多くのお客様からお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。
お客様の事業拡大を通じて、当事務所も共に成長していくこと、これが私の目標でもあり、夢でもあります。
2020年も多くのお客様と出会い、支援できることを願っております。
2020年も皆さまにと
続きを読む >>
新しい請求書等保存方式について
令和元年10月からの消費税率引上げに伴う軽減税率制度の実施により、複数税率になるため日々の取引や経理事務において従来の記載事項に加え、新たに税率ごとの区分を記載した請求書等の交付や保存、税率ごとに区分した記帳などの経理が必要になります。以前にも一部掲載させていただきましたが、前回と今回で、特殊な事項について詳しくお伝えさせていただきます。
(1)「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった
続きを読む >>
M&Aメディア≪FUNDBOOK≫への寄稿のお知らせ
この度、 M&AアドバイザーとM&Aプラットフォームを
組み合わせた「ハイブリッド型」のM&A仲介サービスを行っている株式会社FUNDBOOK(URL:https://fundbook.co.jp/) の運営するM&Aメディアに記事を寄稿させて頂きました。
■記事の内容:
「経営者も知っておきたい株式交換の税務と仕訳」
記事URL: https://fun
続きを読む >>
繰延資産の範囲と取扱い
「繰延資産」というと、資産の繰延をイメージし、前払費用を思い浮かべる人も多いかと思います。「繰延資産」は、サービスの提供を受けた費用であるものの、その効果が一年以上に及ぶものをいいます。一方、「前払費用」は、まだサービスの提供を受けていない費用である点で、繰延資産とは大きく異なります。
繰延資産は、効果が及ぶ期間にわたって費用処理するのが適切と考えられるので、サービスの提供を受けたときではなく
続きを読む >>
消費税の軽減税率制度・新しい請求書等保存方式
10月1日よりスタートした消費税の軽減税率制度ですが、前回は、軽減税率制度が適用される項目について解説いたしました。今回は、前回説明が出来なかった詳細な区分(軽減税率が適用されるか、10%が適用されるか?等)について、Q&A形式で説明いたします。また、複数税率になるため日々の取引や経理事務において従来の記載事項に加え、新たに税率ごとの区分を記載した請求書等の交付や保存、税率ごとに区分した
続きを読む >>
年末調整関係書類 (令和2年に変更予定)
(1)令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申告書」を提出しなければならないとされたことから、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されました。
(2) 令和 2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
地方税法の改
続きを読む >>
民法(相続法)改正
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続き法の一部を改正とする法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
(1)相続法の改正
民法には人が死亡した場合等に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、このルールは
続きを読む >>
法人にかかる税制
(1)法人が有する仮想通貨の評価方法等の整備
仮想通貨が棚卸資産に該当しないことが明確化された上で、法人が期末に保有する仮想通貨の評価方法等が定められました。
①
法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上することとされました。
②
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
続きを読む >>
補助金・助成金
補助金とは、国の政策目標を達成するために、事業者がその目的にあった事業に広くしっかりと取り組んでもらうための、事業の実施のサポートをするための給付金のことです。
一方、助成金とは、国が行っている、雇用関係の助成金を指すのが一般的となります。
(1)補助金・助成金の比較
① 補助金の特徴
期間内に応募して採択されたら支給されるもので、助成金と同様に返済義務がありません。期間内に応募しな
続きを読む >>
法人事業税の税率の改正等
地方法人課税における税源の偏在を是正する措置について、消費税率10%への引上げ段階で地方法人特別税・譲与税が廃止され、法人事業税に復元されること等も踏まえて、見直されました。
法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の標準税率が次のとおりとされ、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度からの適用とされました。
■法人事業税の税率の改正
資本金の額
又は
出
続きを読む >>